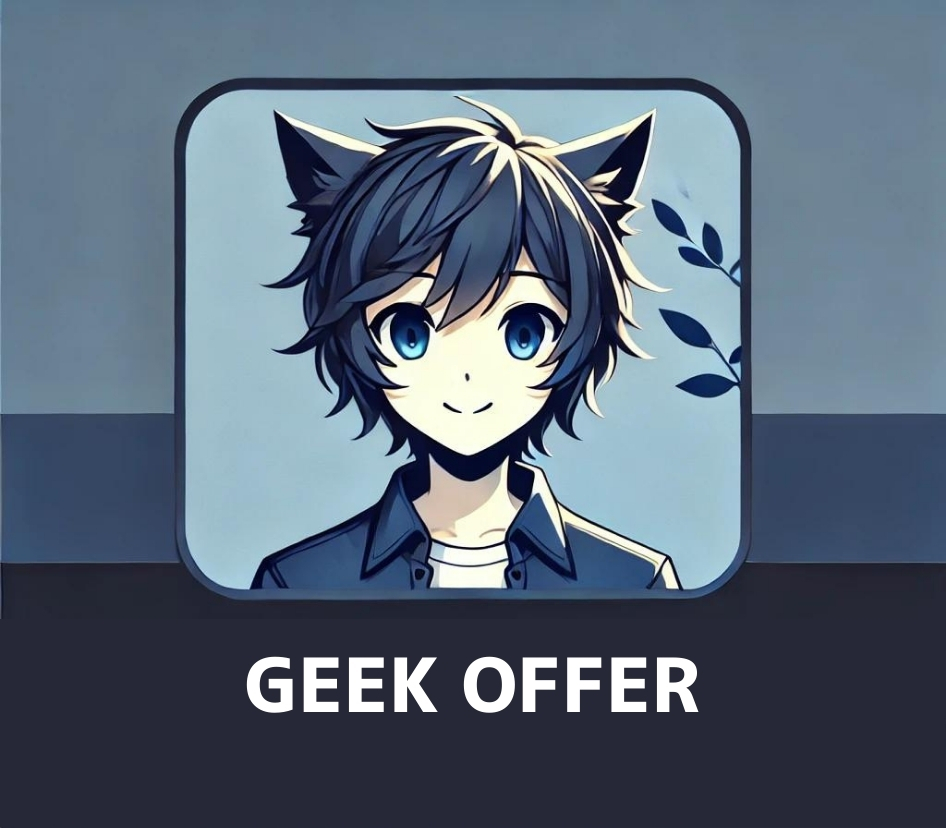
GEEK OFFER運営
山下俊介
GEEK OFFER運営事務局。エンジニアのキャリアに関する情報を幅広く発信。Twitterフォロワー1,200人、Qiita総いいね数3,000
エンジニア就職活動の最初の関門はレジュメです。エンジニア就職・転職の選考ステップ全体の中では比較的重要度が低く見られがちなレジュメですが、実は十分対策している人とそうでない人で、最終的に内定できるか?という点で大きく差がつくポイントです。
しかし、いいレジュメの書き方を知っている人は多くありません。それどころか、どうすれば質の高いレジュメになるのか?というレジュメの勘所を理解している人はごく一部です。
この記事を読むことでいいレジュメが何かわかるようになり、自身の就職活動・転職活動に必ず役立つものが得られるはずです。
対象読者
- 外資系エンジニアの就職・転職を考えている方
- メガベンチャーやスタートアップへの就職・転職を考えている方
X-Y-Z Formulaを活用したエンジニア就活・転職のレジュメテンプレートも無料配布しているので気になる方は記事の最後をご覧ください。
1|エンジニア就職・転職におけるレジュメとは
エンジニア就活・転職におけるレジュメ(Resume)は、一般的な就職活動における職務経歴書とは異なります。就職活動時によく使用する職務経歴書は今までの学歴、経歴を全て記載することが多いです。一方で、エンジニア就職活動におけるレジュメは応募企業にアピールしたい内容をPDF1枚程度でまとめたものを指します。
つまり、自身のアピールポイントや経験を端的にまとめたプロフィールのようなものがエンジニア就職活動におけるレジュメです。
まずはエンジニア就職活動を俯瞰したときのレジュメの立ち位置について解説します。
エンジニア就活でのレジュメの立ち位置
エンジニア(ソフトウェアエンジニア、AIエンジニア)就活の一般的な選考プロセスは、大きく下記の4つのステップに分かれています。
1. レジュメ選考(書類選考)
2. コーディングテスト
3. 面接
4. 内定レジュメ選考は就活全体の選考ステップの最初に位置しています。
就職活動や転職活動で企業に応募した場合、企業はまずレジュメを見ます。その中でもっと詳しく話してみたいと思った応募者が次の選考ステップに進めます。
エンジニア就活・転職におけるレジュメの重要度は、その後の選考の重要度ほど高くはない場合が多いですが、時間をかけて質の高いレジュメを準備することは応募先の企業の書類選考を通過する以外の点でも非常に効果的です。
具体的にどのようなメリットがあるのかについて下記で解説します。
質の高いレジュメを作成するメリット
高品質なレジュメを作ることによる嬉しいポイントは下記の3点です。
1. 応募企業のレジュメ選考の突破率が上がる
2. 自分が行きたい企業に積極的に応募することができる
3. 自然と面接対策になっているそれぞれ具体的に説明します。
1. 応募企業のレジュメ選考の突破率が上がる
質の高いレジュメを作成し、提出した書類を通じて応募企業に自身の経験や魅力をアピールできれば、レジュメ選考の通過率は当然上がります。アピールが不十分であったり、お作法に則っていないレジュメを提出している方も多いので、しっかりと準備するだけお得です。
2. 自分が行きたい企業に積極的に応募することができる
一見先ほどの項目と同じことを言っているように見えますが、違います。
先ほどとの違いは、LinkedInやTwitterなどで個別に企業とコンタクトする時にもレジュメが活躍するという点です。
近年はSNS経由で企業と接点を持つことが増えてきました。
もちろん、何の準備もなくメッセージを送っても相手にされません。
「なぜ自分と面接すべきか?」ということを端的に伝える(自分を売り込む)ことで初めて興味を持ってもらい、面談や選考を行なってもらえます。
そのための『証明書』として使えるのが質の高いレジュメです。
質の高いレジュメを準備することで、自分をなぜ採用すべきか?というメッセージと熱意を同時に伝えることができます。
極端な話ですが、公に求人が出ていない企業でも場合によっては選考ルートを用意してもらえるケースもあります。
筆者は、実際に自分でレジュメを作成し、LinkedInで気になっている企業の担当者にコンタクトを取って特別に選考をしてもらい働かせていただいた経験があります。
3. 自然と面接対策になっている
レジュメ作成だけに注目すると見落としてしまいがちですが、
Technical Interview(技術面接)であれ、Behavioral Interview(行動面接 / STAR面接)であれ、エンジニア採用の面接ではレジュメの内容を深掘りすることが一般的です(これをResume Deep Diveといいます)
面接官はレジュメに記載されている内容から、候補者のエンジニアとしての素養を測るために様々な角度から質問や深掘りをします。
レジュメの内容をもとに深掘りがされるのであれば、あらかじめ質の高いレジュメを準備することが結果的に面接対策になることも納得がいくと思います。
詳しい対策方法については、面接対策系の記事でご紹介します。お楽しみに!
質の高いレジュメを作成することの恩恵が分かったところで、具体的にどうすれば質の高いレジュメを準備できるのか?という点を解説していきます。
冒頭に紹介した通り、本記事ではGoogleが公認しているレジュメの記載方法『X-Y-Z Formula』を詳しく解説していきます。
2|Google公認のX-Y-Z Formulaとは
X-Y-Z Formulaとは、レジュメの品質を向上させる公式のようなものです。X、Y、Zの各要素に自身の経験などを当てはめることで、簡潔かつ具体的に自身の経験をアピールすることができる構文となっています。
まずはX-Y-Z Formulaがどんなものか、実際に構文を見てみましょう。
[Z]という取り組みによって、[Y]という指標で評価される、[X]という項目を達成した。英語だと、
Accomplished [X] as measured by [Y], by doing [Z].のようになります。
X、Y、Zにはそれぞれ下記の項目を当てはめます:
X:開発タスクを通じて達成した取り組みと具体的な数値
Y:取り組みの成果を測る指標
Z:成果を上げるために工夫したポイント
自身の開発経験を「[Z]というオリジナルの工夫によって、[Y]という評価指標を[X]だけ改善した」のような表現で、具体性を持たせながら簡潔にまとめることができるのがX-Y-Z Formulaの強みです。
一見しただけでは何が凄いのか?が掴みにくいと思うので、メリットや具体例をそれぞれ解説していきます。
ちなみにX-Y-Z Formulaができた背景はこちらです。Googleは毎年全世界から数万人の応募がある企業です。各々自由な形式でレジュメが提出されて選別に手間がかかっている状況にGoogleがお怒り(意訳)になり「全員この書き方に従ってください!」という表明を出したことが始まりとなっています。
X-Y-Z Formulaを活用するメリット
X-Y-Z Formulaを活用する主なメリットは下記2点です。
1. 自身の経験を最大限アピールした文章ができる
2. 自然と構造化された文章になるので、論理性のアピールにもつながるそれぞれ順番に説明します。
1. 自身の経験を最大限アピールした文章ができる
X-Y-Z Formulaを使うことで、自身の開発経験を最大限アピールすることができます。
Xには自身の達成した具体的な内容、Yにはその評価指標、Zは成果を上げるための工夫を当てはめます。
「何を」「どうやって」達成したのか、そしてそれは「どの程度すごいことなのか?」について一文で説明できるので読み手にとっても非常に読みやすい文章になっています。
企業側がレジュメの段階で知りたい情報と、応募者がレジュメに記載した情報(アピールしたい情報)がずれてしまうケースはよく発生します。本来魅力的な開発経験をしていて、実力もあるにもかかわらずレジュメで落ちてしまうのは、自身が書きたい内容と相手が知りたい内容のアンマッチが主な原因です。
そのようなパターンを避けるためのガードレールのような機能もX-Y-Z Formulaは果たしてくれます。
2. 自然と構造化された文章になる
X-Y-Z Formulaを使うと、自然と「何を」「どうやって」「どの程度達成したのか?」という要素が含まれて整理された文章になります。
普段レジュメを添削している中で
- 文章を長々と書いてしまい結局何を伝えたいのかが判断しにくい
- レジュメ段階で必要以上に技術に深入りしている
のような特徴のレジュメに多々目にします。
1. 文章を長々と書いてしまい結局何を伝えたいのかが判断しにくい
こちらは論理力、構造化力に対してネガティブな印象を持たれる可能性があります。
「結論を先に伝え、必要に応じて適宜深く情報を伝えていく」という順番は意外とできていない方が多いです。チームが開発が基本である以上、ビジネスコミュニケーションは意識しておくべきです。
一朝一夕でできることではないと思うので、レジュメ作成においても常に意識をしておくと良いです。
2. レジュメ段階で必要以上に技術に深入りしている
こちらは技術に明るい点は非常にプラスポイントなのですが、相手の全体像が把握できていない中で特定の箇所だけの情報量を増やしてしまうのは少々危険です。
そのような内容はレジュメではなく、その後の選考ステップで面接官との対話の中でアピールしていくのが好印象です。
X-Y-Z Formulaを使うと特定の場所に必要以上に深く入り込んでしまうことを防ぐことができます。
ここまでのまとめ:
- 自身の経験を最大限アピールした文章ができる
- 自然と構造化された文章になり、論理性をアピールできる
X-Y-Z Formulaの概要とメリットを掴んだところで、いよいよ具体的な運用方法に入っていきましょう。
X-Y-Z Formulaの使い方
次は、エンジニア就職・転職におけるX-Y-Z Formulaの使用方法を複数の具体例を交えながら解説していきます。
下記2つの開発タスクを題材にして、それぞれ松・竹・梅の3段階の使用例を用いて説明します。
1. 社内検索エンジンの精度向上タスク
2. 画像分類システムの開発タスクパターン①:社内検索エンジンの精度向上タスク
梅:社内検索エンジンの精度を向上させた
竹:社内検索エンジンの精度を30%から90%まで向上させた
松:Elasticsearchを活用して自社データでチューニングを行うことで、社内検索エンジンの精度を30%から90%まで向上させた
それぞれ見てみると、違いが一目瞭然だと思います。
X-Y-Z Formulaと照らし合わせると、
梅:Xのみ言及している
竹:XとYに言及しているが、Zに言及できていない
松:X、Y、Z全てに言及できているという構造になっています。
パターン②:画像分類システムの開発タスク
梅:画像分類タスクにおいてモデルを開発し、分類精度を向上させた
竹:画像分類タスクにおいてモデルの精度を85%から94%に向上させた
松:データ拡張(Data Augumentation)とResNet50をベースにした転移学習を組み合わせることで、画像分類タスクにおいて分類精度を85%から94%に向上させた
企業側がこれを読んで「この応募者はこういうタスクだったらこれくらいの結果を出してくれるかもしれない」のように思わせることができれば、まず問題なく次のステップに進むことができます。
例を参考にしながら、自身の経験に置き換えて文章を作成してみてください。
この章では、X-Y-Z Formulaの概要、メリット、具体例を解説しました。
X-Y-Z Formulaを活用することで一段質の高いレジュメに近付くと思います。
もちろん、一度作成して終わりではなく普段の業務などの中で得られた経験を盛り込みながらブラッシュアップすることを意識してみると良いと思います。
3|まとめ
今回の記事では自身のレジュメをレベルアップするX-Y-Z Formulaについて解説しました。
X-Y-Z Formulaを活用することで簡潔かつ具体的に自身の経験を相手に伝えられる構成になっていますが、これだけでレジュメ全てが完璧というわけではもちろんありません。
レジュメ対策をすることで、足元の書類選考突破だけでなく、新たな可能性が広がったり、面接対策もできるなど、一石二鳥、一石三鳥の超コスパの良い対策なのでぜひおすすめします。
他に気をつけるべきポイントやレジュメの全体像については別の記事で解説するのでぜひご覧ください。
4|おまけ
GEEK OFFERでは「X-Y-Z Formulaを活用したレジュメテンプレート」を無料配布しています。
他にも、エンジニア就職・転職に役立つ情報や対策サービス、求人情報を届けているのでぜひ会員登録してチェックしてみてください。
▼ 会員登録はこちら:
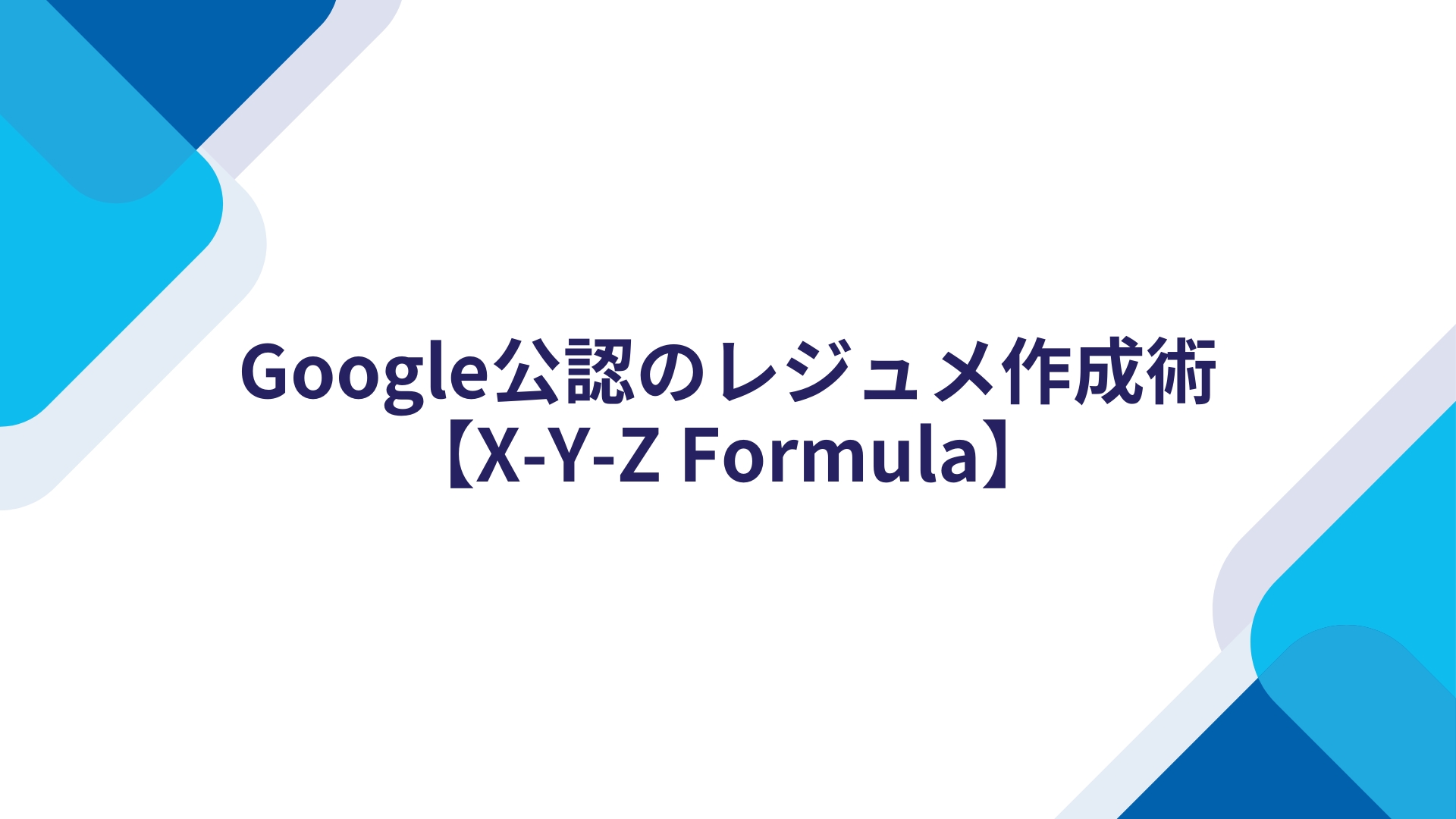
コメントを残す